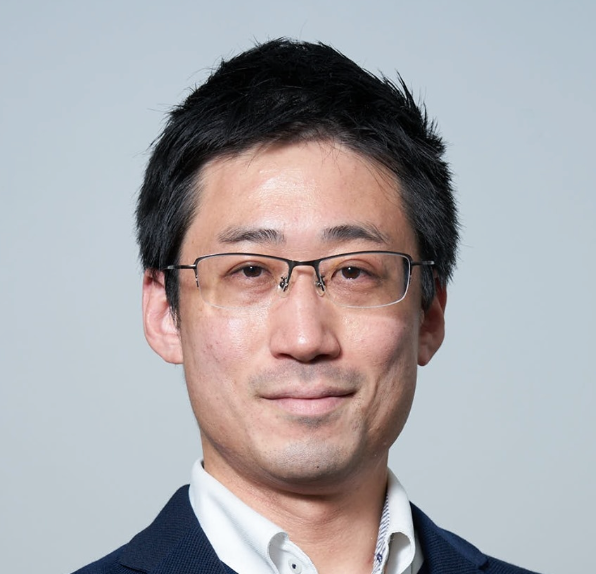次世代のマテハン「物流ロボット」を解説!導入のメリットと注意点

「近年、倉庫DX推進の流れをひしひしと感じるが、人手不足が深刻化する今後の物流業界を考えると既存のマテハンだけではなくロボットも導入した方が良いのだろうか?」
「そもそもマテハンとロボットの違いがよくわからない。具体的にどのようなロボットがあるのか?」
自社倉庫の未来に漠然とした不安を感じ、このような疑問をお持ちの企業様も多いのではないでしょうか。
物流業界におけるマテハンとは、物流業務の省人化・品質向上を促進する機器の総称であり、その中でも人間に代わり自律的に動いて作業を行う機械のことを「物流ロボット」と呼びます。
その他、マテハン・ロボットに関する基礎知識として押さえておきたい情報を以下の表にまとめました。
| 物流業界におけるマテハン・ロボットの基礎知識 | |
| マテハンとは? | 物流業務の省人化・品質向上を促進する機器の総称
※フォークリフト・コンベアといった簡易的なものから最新の物流ロボットまで、全て含めて「マテハン」 |
| ロボット(物流ロボット)とは? | 人間に代わり自律的に動いて作業を行う機械のこと |
| 物流ロボットにはどんな製品がある? |
|
| 物流ロボットを導入するメリットは? |
|
| 物流ロボットを導入するデメリットは? |
|
| 物流ロボットを倉庫に導入するべきか? | 「とりあえず」で導入は危険!慎重なリサーチと検討が必要
※メーカーに問い合わせる前に、まずは外部コンサルなどの第三者に相談するのがお勧め |
物流ロボットの導入は倉庫の省人化に効果的である一方で、コストが高く既存のマテハンやシステムとの連携が上手くいかないリスクもあります。
「とりあえず最新の物流ロボットを導入してみたが、高いコストと労力をかけた割に思ったような効果が得られなかった」
といった失敗ケースも考えられるため、慎重に検討するべきだと言えるでしょう。
本記事では、物流業界におけるマテハン・ロボットについて知りたい企業様に向けて、
・マテハン・ロボットの違いと関係性
・物流ロボットの種類(業務工程別)
・物流ロボットを倉庫に導入するメリット・デメリット
といった情報をわかりやすく解説します。
マテハン・ロボットに関する知識が整理され、自社倉庫に導入すべきかどうかの方向性が定まりやすくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。
【記事監修】園田真之介
Rally Growth株式会社 代表取締役社長。株式会社FrameworxでSEとしてキャリアを形成後、株式会社BayCurrent Consultingを経て現職。専門は物流・ロジスティクス×IT領域。過去に大手アパレルの物流・倉庫最適化や大手自動車メーカーの物流システム刷新の案件をコンサルタントとして多数経験。2021年グロービス経営大学院卒(MBA)
1. 物流業界におけるマテハンとは?ロボットとは?違いや関係性を解説

まずは、物流業界における「マテハン」と「ロボット」の違いや関係性について、以下の順にお話しします。
・マテハンとは
・ロボットとは
・従来型マテハンと物流ロボットの違い
マテハンとロボットの境界は非常に曖昧であり、明確に分類することは容易ではありません。
本章では画像等を使ってできるだけわかりやすくお伝えしますので、今後の倉庫運用を考える際の基礎情報としてご活用ください。
1-1. マテハンとは
マテハンとは「マテリアルハンドリング」の略称で、物の移動や仕分けなどの作業そのものを指す言葉です。
しかし、今日の物流業界においては物流業務の省人化・品質向上を促進する「マテハン機器」の総称を指して「マテハン」と呼ぶのが一般的であり、本記事でもそのように定義しています。
マテハンと呼ばれる機器の定義は非常に幅広く、古くから倉庫現場で使われているコンベヤやフォークリフトはもちろんのこと、最新の物流ロボットまで全て「マテハン」に該当します。

倉庫運用に使用する機器は、基本的に全て「マテハン」に含まれると認識しておくと良いでしょう。
1-2. ロボットとは
物流業界におけるロボットとは、倉庫や物流センターで人間に代わり自律的に動いて作業を行う機械のことで、「物流ロボット」と呼ぶのが一般的です。
数あるマテハン機器の中でも、自律的に動く機能を搭載した
・AMR(自律走行搬送ロボット)
・AGF(無人フォークリフト)
・ソーティングロボット
・ピースピッキングロボット
などが「物流ロボット」に分類されます。
つまり、物流ロボットも広い意味ではマテハンの一種ということになりますが、あえて分類するのであれば
・昔ながらの人間が操縦・操作するマテハン→「従来型マテハン」
・自律的に動くマテハン→「次世代型マテハン(=物流ロボット)」
の2つに分けるとイメージしやすいでしょう。
1-3. 従来型マテハンと物流ロボットの違い
従来型マテハンと物流ロボットの違いは、一言で言えば「自律的に動くかどうか」です。
具体的には、以下のように分類することができます。
| 従来型マテハンと物流ロボットの分類例 |
| 従来型マテハン |

人間が操作・操縦し、決められた動きをする
自動倉庫など備え付け型の機器は基本的に「従来型マテハン」に分類される |
| 物流ロボット |

移動ルートの選択・障害物の回避などを自ら判断して自律的に動く
|
※磁気テープなどに沿って決められたルートを走行することから、本記事においては無人搬送車を「従来型マテハン」に分類しています。
ただし、マテハンメーカー・Mujinの「モバイルロボット 3D自動倉庫」のように、ロボット的な機能(保管効率を自動で最大化する等)を備えたマテハンというものも例外的に存在します。
上記の分類はあくまで一般的な例として捉えておくと良いでしょう。
2. 物流ロボットの種類【業務工程別】

続いては、物流ロボットの種類を以下の業務工程別に紹介します。
・搬送作業に使う物流ロボット
・仕分け作業に使う物流ロボット
・ピッキング作業に使う物流ロボット
・積付・荷降作業に使う物流ロボット
自社倉庫に導入するイメージを膨らませやすいよう、実際のロボットの製品名や画像を交えてお伝えするので、併せてご参照ください。
2-1. 搬送作業に使う物流ロボット
搬送作業に使う物流ロボットには、
・AMR(自律走行搬送ロボット)
・AGF(無人フォークリフト)
といったものがあります。
それぞれの特徴や具体的な製品を、詳しく見ていきましょう。
| AMR(自律走行搬送ロボット) | ||

画像出典:ラピュタロボティクス「AMR導入事例 ホンダロジコム株式会社」 |
||
| 特徴 |
|
|
| お勧めメーカー・製品 |
|
|
| AGF(無人フォークリフト) | ||

画像出典:トヨタL&F「Rinova AGF」 |
||
| 特徴 |
|
|
| お勧めメーカー・製品 |
|
|
2-2. 仕分け作業に使う物流ロボット
仕分け作業に使う物流ロボットには、仕分け機の中でも「ソーティングロボット」と呼ばれるものが該当します。
ソーティングロボットの特徴やお勧め製品は以下のとおりです。
| ソーティングロボット | ||

画像出典:+Automation「t-sort」 |
||
| 特徴 |
|
|
| お勧めメーカー・製品 |
|
|
※「t-sort」は中国メーカー・リビアオの製品だが、トヨタL&F・+Automation等の代理店でも取り扱われている
ソーティングロボットは、ソーター・DAS・DPSといった人間が操作したとおりの決められた動きをする従来型マテハンよりも柔軟性が高いのが特長です。
商品サイズや仕分け先が多様な倉庫現場においては特に、省人化・生産性の向上が期待できると言えるでしょう。
2-3. ピッキング作業に使う物流ロボット
ピッキング作業に使うマテハンの中では、「ピースピッキングロボット」と呼ばれるものが物流ロボットに該当します。
ピースピッキングロボットがどのようなものか、詳しく見てみましょう。
| ピースピッキングロボット | ||

画像出典:Mujin「ピースピッカー」 |
||
| 特徴 |
|
|
| お勧めメーカー・製品 |
|
|
従来のピッキングシステムでは、商品を棚から見つけてくる等の一部の作業を自動化できても、最終的には人間の手によるピッキングが必要でした。
ピッキングロボットを導入すれば、倉庫によっては人の手を介さない完全自動化のピッキングが実現できるケースもあり、従来マテハンに比べて大幅な省人化が期待できます。
2-4. 積付・荷降作業に使う物流ロボット
積付・荷降作業に使う物流ロボットには、
・ロボットパレタイザ/デパレタイザ
・バンニング/デバンニングロボット
といったものがあります。
それぞれの特徴や具体的な製品を、詳しく見ていきましょう。
| ロボットパレタイザ/デパレタイザ | ||

画像出典:オークラ輸送機「ロボットパレタイザ」 |
||
| 特徴 |
|
|
| お勧めメーカー・製品 |
|
|
| バンニング/デバンニングロボット | ||

画像出典:XYZ Robotics「導入事例 | RockyOneがEurovoの出荷業務を最適化」 |
||
| 特徴 |
|
|
| お勧めメーカー・製品 | ||
このように、物流ロボットには、各作業工程で活用できる様々な製品が存在します。
3. 物流ロボットを倉庫に導入する4つのメリット

ここからは、物流ロボットを倉庫に導入する4つのメリットについて解説します。
・人手不足を解消できる
・人件費が抑制され長期的にはコスト削減につながる
・従業員の身体的負担・怪我や事故のリスクを軽減する
・生産性が向上する
物流ロボットが自社倉庫に導入する価値はありそうなのかを把握するために、まずは具体的にどのようなメリットがあるのかを把握しておきましょう。
3-1. 人手不足を解消できる
物流ロボットを導入するメリットとして最も代表的なものと言えるのが、人手不足を解消できるという点です。
これまで手作業(または人が操縦・操作するマテハンでの作業)で行ってきた業務をロボットで完全自動化することで、倉庫の省人化が実現します。
具体的に物流ロボットの導入が人手不足の解消にどうつながるのか、以下の例を見てみましょう。
| 物流ロボットの導入が人手不足の解消につながる例(イメージ) |
| 積付・積降作業の人手不足に悩んでいたA社の場合 |
【ロボット導入前】
|
【ロボット導入後】
|
近年、物流業界では
・労働人口の減少
・物流の小口・多頻度化
・EC市場の拡大
といった傾向が問題視されており、5年後、10年後の未来を見据えると倉庫の省人化は必須だと言えます。
物流ロボットの導入は、今後人手不足が加速していく倉庫にとって大きなメリットをもたらす打開策となるでしょう。
3-2. 人件費が抑制され長期的にはコスト削減につながる
長期的にはコスト削減につながるというのも、物流ロボットを導入する大きなメリットです。
物流ロボットの導入を検討している企業様の中には
「直近の経営状況の改善に繋がるような人件費の抑制をしたい」
とお考えの場合もあるかもしれませんが、物流ロボットは導入時に多額のイニシャルコストがかかるため、なかなか短期でのROI(投資対効果)が出ないという実情があります。
しかし、これまで人間が行っていた作業をロボットに代替することで、倉庫運用のランニングコストの大半を占める人件費を抑制できるのも事実です。
そのため、物流ロボットの導入を「将来のコスト削減のための投資」として捉えておくと、コスト面でのメリットを感じやすいでしょう。
物流ロボット導入によるコスト削減を狙うのであれば、
・経営に過度な負担をかけない範囲の予算をどのくらい確保できるか
・赤字から黒字に転じるまでの体力が自社倉庫にあるか
といった点を押さえながら導入計画を立てることが重要です。
3-3. 従業員の身体的負担・怪我や事故のリスクを軽減する
従業員の身体的負担・怪我や事故のリスクを軽減するというのも、物流ロボットを導入するメリットの一つです。
重い荷物の運搬や事故の起こりやすい機器の操縦など、危険の多い業務をロボットで代替することで、従業員の安全を確保できます。
物流ロボットの導入によって従業員の負担やリスクを軽減するケースにはどのようなものがあるか、以下の具体例をご覧ください。
| 物流ロボットが従業員の負担・リスクを軽減した例(イメージ) |
| フォークリフトの転倒や接触事故に不安があったB社の場合 |
【ロボット導入前】
|
【ロボット導入後】
→事故のリスクが大幅に軽減 |
このように、安全性の高い倉庫運用ができるのは、物流ロボット導入の大きなメリットと言えるでしょう。
3-4. 生産性が向上する
物流ロボットを倉庫に導入するメリット、最後は「生産性が向上する」です。
これまで人の手や半自動のマテハンで行ってきた業務を完全自動化することで、作業スピードの向上や作業品質の安定が期待できます。
実際に物流ロボットによってどれほどの生産性向上が見込めるかは、導入する製品の種類や台数によって異なりますが、イメージの参考に以下の事例をご覧ください。
| 物流ロボットの導入によって生産性が向上した事例 |
| ソーティングロボットの導入で、1日に仕分けられる商品の数が2.5倍に増加 |
【ロボット導入前】
|
【ロボット導入後】
|
このように、物流ロボットの導入は倉庫の生産性を向上させる効果が期待できます。
|
【注意】自動化することでかえって生産性が落ちるケースもある 物流ロボットの種類によってはかえって作業の生産性が落ちるケースもあるため、注意が必要です。 例えば、人が運転するフォークリフトは時速10~15kmほどまでスピードを出せますが、AGF(無人フォークリフト)の運転速度は時速5~8kmほどで、自動化することで作業スピードが落ちる可能性が高いと言えます。 また、複雑な作業の場合はロボットで代替することにより処理速度が遅くなり、人の手の方が早く作業できるというケースも少なくありません。 以上のことから、物流ロボットを導入する際は
を検討したうえで選定すると良いでしょう。 |
4. 物流ロボットを倉庫に導入する3つのデメリット

続いては、物流ロボットを倉庫に導入する3つのデメリットを以下の順にお伝えします。
・イニシャルコストがかかる
・環境を整える手間と時間が必要
・既存マテハンとの連携が上手くいかないリスクがある
メリットとデメリットの両面から物流ロボットを捉え、導入する価値があるかどうかの判断にお役立てください。
4-1. イニシャルコストがかかる
物流ロボットを倉庫に導入するデメリットとして最も代表的なのが、イニシャルコストがかかることです
具体的な金額は導入するロボットの種類・台数・規模等によって変わりますが、おおまかな本体価格の相場は以下のとおりです。
| 物流ロボットの本体費用(目安) | |
| ロボットパレタイザ | 200~1,000万円/台 |
| AGF | 1,000~2,000万円/台 |
| AMR | 300~1,500万円/台 |
さらに、物流ロボットを導入する際には上記の本体費用に加えて、
・メンテナンス費用
・インフラ整備費
・ロボットを制御するためのシステム導入費
といったコストもかかります。
ご参考までに、当社がAGF導入に向けて見積もりを取得した時の費目を以下でご紹介します。
|
【本体費用以外に発生する費目例(AGFの場合)】
※初期設定費の内訳:設計費・システム設定費・付属品費・現地工事費・試運転調整費 ※カスタマイズ費用の内訳:外部機器連携・パーツ単位のカスタマイズ・対応パレット数の増加 など |
このように、物流ロボットには多額の費用がかかることから、導入に消極的になる企業は多いです。
「将来のために物流ロボットを導入したいが、数千万~数億円の費用などとても出せない」
といった状況であれば、
・補助金の活用
・海外製ロボットの活用
といった選択肢を視野に入れることをお勧めします。
| コスト面で物流ロボット導入をためらう企業に有効な選択肢 | |
| 補助金の活用 | |
| 国土交通省では、「物流施設におけるDX推進実証事業」として、物流施設におけるシステムの構築や自動化・機械化機器の導入を同時に行うことで補助金を受け取る企業を公募しています。
※補助対象メニュー
詳しくは、国土交通省のWebサイトをご確認ください。 ※参考:国土交通省「物流施設におけるDX推進実証事業 事業説明資料」(p.9) |
|
| 中国製物流ロボットの活用 | |
| 中国のマテハン市場は日本に比べて圧倒的に大きく、自動化の技術も進んでいることから、安価なマテハン機器が多く流通しています。
ただし、中国メーカーから直接購入した場合日本の市場に合ったサポート・サービスを十分に受けられない可能性があるため、海外製マテハンの取り扱いに慣れた日本国内の代理店を通じて導入することをお勧めします。 |
4-2. 環境を整える手間と時間が必要
環境を整える手間と時間が必要というのも、物流ロボットを倉庫に導入するデメリットのひとつです。
物流ロボットを導入する際、搬入から稼働させるまでに以下のような準備が必要になります。
| 物流ロボットの導入に必要な準備(一例) | |
| ネットワーク通信環境の強化
ロボットの安全な走行・障害物検知のために必要なWi-Fiや5Gなどの通信基盤を整備する |
|
| 倉庫の床面・レイアウト整備
ロボットが走行・稼働しやすいよう段差や傾斜・障害物をなくして動線を確保する |
|
| 既存マテハンやシステムとの連携
すでに倉庫で稼働させているマテハンやWMS等のシステムとデータ連携し、業務全体を最適化する |
|
| 業務フローの再設計
ロボットに合わせてこれまでの作業手順を見直し、人と機械の役割分担を整理する |
自動倉庫などの大型マテハンのように大規模な工事をせずに導入できるのが物流ロボットの強みではありますが、それでも受け入れるためには相応の時間と手間が必要です。
特にWMS・WES・WCSといったシステムにカスタマイズ・リプレイスが必要になった場合は、数カ月~1年以上の時間がかかるケースもあります。
以上のことから、物流ロボットの導入はできるだけ早い段階で検討・プランニングすることが重要だと言えるでしょう。
4-3. 既存マテハンとの連携が上手くいかないリスクがある
既存マテハンとの連携が上手くいかないリスクがあるというのも、物流ロボットを倉庫に導入するデメリットのひとつです。
この記事を読んでいる企業様の多くは、すでに自社倉庫でマテハンを導入し、ベンダーとも契約されているのではないでしょうか。
ここに新たに物流ロボットを導入することで、
・システム上の連携
・業務上の連携
といった2つの面での連携に不具合が生じるリスクがあります。
一体どういうことか、詳しく解説した以下のケースをご覧ください。
| 物流ロボットと既存マテハンの連携が上手くいかない2つのケース | |
| システム上の連携が上手くいかないケース | |
※ベンダー同士の連携・追加開発等で対応できる場合もあるが、多額の費用や時間がかかる |
|
| 業務としての連携が上手くいかないケース | |
|
このように、選ぶロボットやベンダーによっては既存マテハンとの相性が悪い場合もあるため、導入前には十分な検討が必要です。
5. 物流ロボットは既存マテハンや人間と共存させるのが一般的!組み合わせ例を紹介

ロボットの導入は倉庫の省人化や生産性の向上が期待できることから物流業界で注目されていますが、その一方で多くの企業にとっては倉庫の「完全自動化」はまだまだ難しいというのが現状です。
そのため、倉庫現場の課題に合わせて部分的に物流ロボットを導入し、
・人(従業員)
・従来型マテハン
・物流ロボット
の三者を組み合わせて運用するというのが現実的な倉庫DXの推進ルートだと言えるでしょう。
人×従来型マテハン×物流ロボットをどう組み合わせれば良いのか、以下の例をご覧ください。
| 人×従来型マテハン×物流ロボットの組み合わせ例 | ||
| ピッキング業務の生産性・積付業務の安全性に課題があるC社の場合 | ||
【基本の倉庫業務フロー(物流ロボット導入前)】
倉庫の課題:ピッキングに時間がかかる・積付時の事故リスクが心配 →ピッキングロボット・ロボットパレタイザを導入 |
||
【物流ロボット導入後の業務フロー】
→ピッキングと積付の作業効率が向上・フォークリフトによる事故のリスクも低減した |
このように倉庫の課題に合わせて物流ロボットを部分的に取り入れ、人による手作業・既存マテハンと組み合わせ連携させることで、「自社にとってベストな倉庫運用」ができるようになります。
6. 「とりあえず」で導入は危険!物流ロボットの導入は慎重なリサーチと検討が必要

これまでマテハン・物流ロボットに関する様々な情報をお伝えしてきましたが、
「結局物流ロボットは導入するべきなのか?」
という疑問に対しては
「『とりあえず』で導入するのは危険。物流ロボットの導入は慎重なリサーチと検討が必要」
というのが本記事の結論です。
物流ロボットの導入が成功するか失敗するかは
・既存マテハンシステムとの相性
・選ぶ製品やメーカー
・現在の倉庫の環境(設備・人員など)
といったあらゆる要因によって左右されるため、期待していた効果が出るかは稼働させるまでわかりません。
導入前には慎重なリサーチ・検討が重要であり、具体的には以下のような作業が必要になります。
|
【物流ロボットの導入前にやっておくべきリサーチ・検討】
|
しかし、上記の内容を物流ロボットのメーカーに真っ先に相談・問い合わせするのはあまりお勧めしません。
これは、メーカーは導入前提で話を進めるので、「貴社にとって物流ロボットの導入が本当に必要なのか」までは検討してもらえないためです。
一方で、専門知識を持たない社内の人間だけで事前のリサーチを行うというのも現実的ではありません。
まずは外部のコンサルなど、第三者の物流のプロに相談するところから始めることをお勧めします。
7. マテハン・ロボットの導入に関する相談なら、物流ITコンサル「Rally Growth」にお任せください!

マテハン・ロボットへのリサーチを進めていくなかで、
「AGVのような決められたルートを走るマテハンか、AMRのような自律的に走行するロボットか、自社倉庫にどちらが適しているかわからない」
「導入してみたいロボットがあるが、既存のマテハンとの相性がわからない」
「メーカーに直接問い合わせる前に、客観的な意見が聞きたい」
といったお悩みをお持ちであれば、「物流を中心とした業務知見の豊富さ」×「IT/機械化の知見・経験」を強みとする「Rally Growth」にご相談ください。
| Rally Growthとは? | |||
| 2021年に創立した、ミドルマーケットを中心としたDX化/新規事業構築支援を行う、ビジネスコンサルティングファームです。
代表の園田を中心に物流業界に知見のあるメンバーが集まっており、主に物流DXに関連する案件を中心に、複数の企業を支援しています。 |

| Rally Growthの強み | |||
| 豊富な知識に基づいた広い視点での企画・提案ができる
これまで物流の改善企画を数多く支援してきた経験から、
など、物流業界の幅広い知識を持っています。 「課題が多岐にわたっていて、何から手をつけて良いかわからない」という場合でも、広い視点での企画・提案ができます。 マテハン機器・メーカーの選定はもちろん、WMSやWCSといった周辺システムとの連携や、現場の根本的な課題を発見するコンサルまでこなす総合力の高さは、他社にはない大きな強みだと言えるでしょう。 【他社との違い比較表】
|
|||
| お客様の支援事例 | |||
【プロジェクト概要】
【プロジェクト背景】 6階建ての延床面積約10万㎡という巨大な専用物流倉庫を建設した同社は、マテリアルハンドリングメーカーと手を組み、RFID(無線自動識別)や自動倉庫、自動搬送機などを取り入れたプロジェクトを発足しました。 【支援内容】 弊社も当プロジェクトに参画し、主に以下3つの支援をさせていただきました。
最適なメーカーを探すべく、メーカー選定に先立って多種多様なマテハンを活用したオペレーションの設計を行っていましたが、既存のクラウド製品ではマテハンとの連携はもちろん、同社の基幹システムとの連携も難しかったため、オンプレミス型かつフルスクラッチでのシステム構築に踏み切りました。 結果として大規模な物流倉庫の立ち上げに成功し、今では日本最大級の省人化倉庫として日々稼働しています。 |
マテハン・ロボットの導入やシステムとの連携には多額のコストがかかり、場合によっては総コストが数千万~数億円にのぼる可能性もあります。
多額の予算を割いて最新マテハンを導入しても、綿密な計画を練らなければ、倉庫業務の改善に十分な効果を発揮させられません。
「自社倉庫の課題と徹底的に向き合い、最適なマテハン・ロボットを選定したい」
「目の前の課題に対処するだけではなく、10年後、20年後も生き残れる倉庫運用がしたい」
と考えている方こそ、まずはお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
Rally Growth株式会社への物流に関するコンサルティング案件のご相談はこちらより承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
※顧客への対応や提案にお困りのマテハンベンダー様も、ぜひ上のフォームからご相談ください。
当社はマテハンベンダー様との協業も視野に入れており、顧客の業務整理からマテハン・システム要求事項の洗い出し、営業フェーズのお手伝いも可能です。
【資料請求】
以下よりRally Growthのサービス資料もご請求いただけます。
ご支援の全体像や具体的なご支援プランを掲載していますので、物流を中心としたDX支援のサービスをご検討の方はぜひご一読ください。
<Rally Growth サービス資料イメージ>
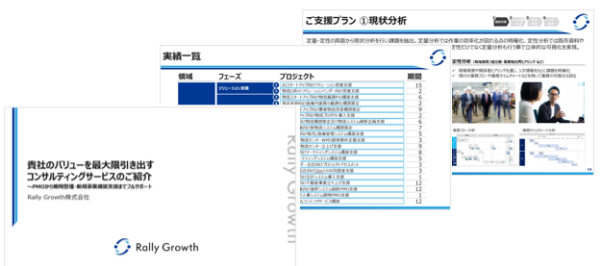
8. まとめ
最後に、本記事の重要ポイントをおさらいします。
▼物流業界におけるマテハンとロボットの違い
| 【マテハン】
物流業務の省人化・品質向上を促進する「マテハン機器」の総称 【ロボット】 倉庫や物流センターで人間に代わり自律的に動いて作業を行う機械 →ロボットもマテハンの一部であり、両者をあえて分類するのであれば「従来型マテハン」「物流ロボット」の2つに分けられる 【従来型マテハン】 人間が操作・操縦し、決められた動きをする機械(有人フォークリフト・AGV・ソーターなど) 【物流ロボット】 移動ルートの選択・障害物の回避などを自ら判断して自律的に動く機械(AGF・AMRなど) →従来型マテハンと物流ロボットの最大の違いは、「自律的に動くかどうか」 |
▼物流ロボットの種類
【搬送用ロボット】
【仕分け用ロボット】
【ピッキング用】
【積付・荷降用ロボット】
|
▼物流ロボットを倉庫に導入するメリット・デメリット
【メリット】
【デメリット】
→物流ロボットを「とりあえず」で導入するのは危険。慎重なリサーチと検討が必要 |
本記事の内容が、貴社の倉庫運用改善のお役に立てましたら幸いです。
- この記事を書いた人
-